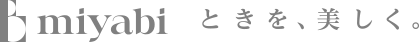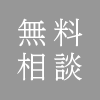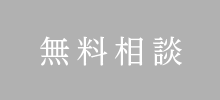マンション選びをする際に、エレベーターの有無は多くの人によって重要なポイントです。特に高層階に住む場合エレベーターがなければ荷物の持ち運びや移動が大変で、日常生活に支障をきたすこともあります。
しかし、エレベーター設置には法律で決められた義務があり、逆に言うとその義務に抵触しない建物には設置しなくても良いとされているため、すべての物件にエレベーターがあるというわけではありません。
今回は、エレベーターの設置条件や義務について詳しく解説してきます。
エレベーター付き無しの物件選びに迷っている方はこの記事を参考にしてください。
エレベーターがあるマンションは最低何階?
マンション探しをしていると、5階建てや6階建てでもエレベーターがない物件や、3階建ての低層マンションでもエレベーターがついている物件などさまざまです。では、エレベーターの設置には基準や決まりがあるのでしょうか。
高さ31mを超える建物はエレベーターの設置義務がある
建物でエレベーターを設置しなければならない基準は、実は階数ではなく高さ。建築基準法(第34条)で、高さ31m超の建物に「非常用の昇降機」、つまり「エレベーター」の設置が義務付けられています。
7~10階建てが高さ31m程度 6階以下の建物に設置義務はない
エレベーターを設置しなければならない「高さ31m超」の建物は、何階建てに相当するのでしょう。建物の階数は建物の高さではなく、それぞれのフロアがどれくらいの高さの空間になっているかで違います。各住戸の天井が高いほど、階数は少なくなりますが、高さ31mのビルやマンションは一般的には7~10階に相当します。
つまり、6階建て以下程度のビルやマンションにはエレベーターの設置義務はありません。でも、4階や5階の住戸でもエレベーターなしの生活は大変。設置義務はないとしても、その建物を利用する人や、暮らす人の利便性考えて設置されているケースが多いのです。
高齢者向け住宅の特別基準
サービス付き高齢者向け住宅などの高齢者向けの共同住宅では上とは別の基準が設けられており、3階建て以上の場合にエレベーターの設置義務が設けられています。これは国土交通省の「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に定められているもので、居間から食堂、浴室など、階をまたぐ移動をより安全にするためです。
エレベーターの有無にはどんなメリットがあるの?
あると便利なエレベーターですが、エレベーターのないマンションにもメリットはあります。エレベーターのあるマンション、ないマンションそれぞれの良さを比較してみましょう。
エレベーター付きマンションの利点
エレベーター付きマンションの最大のメリットは、利便性の高さです。
負担の大きな階段の上り下りが不要になるため、とりわけ高齢者や障がいのある人、小さな子どもがいるファミリーにはメリットが大きいでしょう。
このほか、体調の悪いときやケガをしたとき、たくさんの買い物をしたときなどにもエレベーターがあると楽に自室にたどり着けます。
エレベーターがないマンションの利点
エレベーターがないマンションの場合、「上層階に住むと毎日の上り下りが大変そう」などのデメリットが頭に浮かぶでしょう。
でも、1階や2階など、荷物を持って上り下りするのが苦にならない低層階を選べばエレベーターの有無は日常生活にあまり影響ありません。
「若いうちは運動にもなるし苦にならないはず!」と思ってエレベーターがない物件を選ぶ人もいるでしょう。
エレベーターがある物件に比べて、購入時の価格や、賃貸なら家賃などが安く抑えられる点も大きなメリットです。
そのほか、管理費や修繕積立金が安い、エレベーターのモーター音やエレベーターホールに人が集まったときの騒音がないなどのメリットもあります。
一方で、リセールバリューに影響する点には注意が必要です。
売却しようとしても、エレベーター付きのマンションと比べると買い手がなかなか決まらない可能性もあります。
今の暮らしやコストだけでなく、将来のことも考えて選ぶことが重要です。若いうちは気にならなくても、年をとってきたときには階段が辛くなります。

エレベーター付きのマンションを選ぶときのポイントは?
毎日の生活利便性や将来的な体力の衰え、売却する際のことなどを考えた場合、3~4階以上に長く住むならエレベーター付きの物件を選ぶのがオススメです。ではエレベーター付きのマンションを借りる、または購入する際に、どんなところをチェックすればよいのでしょうか。
安全に利用できるエレベーターの特徴
エレベーターを安全に利用するためには、地震や停電時の対策が不可欠です。2009年9月の建築基準法改正により「P波感知器付地震時管制運転装置と予備電源の設置」が義務付けられました。
マンションの内見時に確認する方法としては、エレベーターに任意で取り付けられた、安全装置設置済マーク(=安全マーク)の表示を確認することです。
もしくは内見の予約をする際に、エレベーターの安全装置について確認したい旨をあらかじめ担当者に伝えておくのがよいでしょう。
※エレベーター安全装置設置済マークについて
https://www.seinokyo.jp/evs/sm/
地震や停電時に近くの階で停止する
安心して利用できるエレベーターには、災害時に対応できる「停電時自動着床システム」「地震時管制運転」「遠隔監視管理サービス」「戸開走行保護装置(UCHP)」などのすぐれたシステムが備わっています。
停電時自動着床システムとは、停電などでエレベーター内に人が閉じ込められてしまった場合、自動的に最寄り階で停まりエレベーターから降りられるというシステムです。また、遠隔監視管理サービスによって、異常情報を管理会社へ送信し迅速な復旧に対応します。
地震時管制運転とは、大きな揺れが発生する前に起こる波動(=P波)を感知すると、最寄り階に着床し扉が開くシステムです。
戸開走行保護装置(UCHP)とは、エレベーターの駆動装置や制御器に故障が生じ、エレベーターの扉が閉じる前に昇降した場合に自動的に制止する安全装置です。これにより、人の挟まり事故を未然に防ぐことができます。
防犯カメラやモニターが設置されている
エレベーター前に「カラーモニター」、エレベーター内に「防犯カメラ」や「防犯警報装置」が設置されているマンションもあります。
防犯警報装置とはエレベーター内で問題が発生した際、防犯ボタンを押すことでブザーを鳴動させ、各階強制停止運転等を行います。
その他、車椅子を利用する方が乗り降りしやすくなるようにエレベーター内に鏡が付いているものもあり、防犯対策としても機能します。
エレベーター内に非常時の設備がある
エレベーター内に防災用具が備蓄されていれば、災害などで万が一閉じ込められてしまっても、救出までの一時しのぎに役立ちます。
防災用具入れは三角柱の形をしているものが多く、一般的にエレベーター内の角にセットされています。中には、水やトイレシートなどが入っており、緊張状態で喉が渇いてしまったり気分が悪くなったりしたときに利用できるので便利です。
安全装置として、停電時の非常灯の設置が建築基準法により義務付けられています。これは「停電灯」と呼ばれるもので、1ルクス(=月明かり程度)以上の明るさの確保が必要とされています。
その他、エレベーター内の奥の壁が鍵で開くように設計されており、担架やストレッチャーなど奥行きのある機材を使ってエレベーターを利用できる構造になっています。病人やけが人の素早い搬送に役立つでしょう。
※建築基準法施行令「エレベーターの安全装置(第百二十九条の十)」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325CO0000000338
さいごに
一般的なマンションのエレベーターは、階数の基準にした建築基準法上での設置義務はありません。高い階数の部屋に住み替えを検討している方は、そのマンションにエレベーターが設置されているか、必ず確認しましょう。
内見時には、防犯カメラや防犯警報装置が設置されているか、防災用具があるか、また安全装置設置済マークを確認するなど、エレベーターの機能性もチェックしておきましょう。
マンション選びでは、部屋の間取りや立地などに目が行きがちですが、エレベーターの存在も忘れてはなりません。ぜひチェックリストに追加しておくことをおすすめします。
私たちmiyabiでは、物件探し・設計デザイン・施工までをワンストップでお手伝いさせていただいております。
お客様の理想の住まいづくりをサポートさせていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
▼▼▼施工事例▼▼▼
miyabi の事例一覧はこちら >>> 施工事例
▼▼▼EVENT▼▼▼
見学会や相談会はこちら >>> イベント
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
資料請求ページはこちら >> Click Here
ご来店問合せはこちら >> Click Here